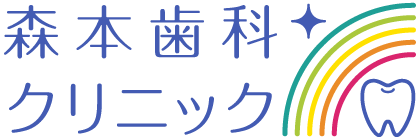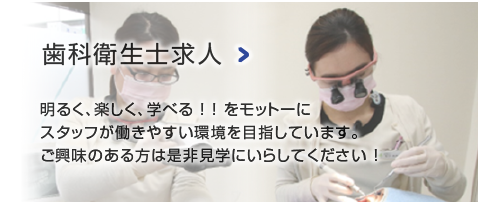みなさんこんにちは!
森本歯科クリニック 歯科助手兼管理栄養士の池田です!
気温が下がり、秋らしい季節になりましたね!
今回のスタッフブログでは「よく噛んで食べることの大切さ」についてお話ししていきます!
現代人は噛む回数が減っている!?
現代では、昔と比べて柔らかい食べ物を好む人が増え、食事にかける時間も短くなっていると言われています。さまざまな時代の食事を再現し、1食あたりの噛む回数を調べた研究によると次のような結果となりました。
弥生時代 3990回
鎌倉時代 2654回
20世紀初頭 1420回
現代 620回
このように、食生活や調理法の変化、食品加工技術の進歩などの影響もあり、現代の噛む回数はわずか半世紀前と比べても大幅に減っていることが分かります。弥生時代と比べると約1/6にまで減っています!
ひ・み・こ・の・は・が・い〜・ぜ
これは日本咀嚼学会が発表している標語で、噛むことの8大効用を示しています。
よく噛むことを意識するとどんないい影響があるのか一つずつ見ていきましょう!
ひ 肥満防止
よく噛まずに食べると食事のスピードが速くなり満腹感を得るまでにたくさん食べてしまい過食につながります。よく噛むことで脳の満腹中枢が刺激され、少ない量で満足感が得られます。
み 味覚の発達
よく噛んで味わうことで食べ物そのものの味がよく分かるようになります。薄味でも満足できるようになり減塩にもつながります。
こ 言葉の発音
よく噛むことで口の周りの筋肉や顎が発達します。自然に正しく口を動かすことができ、表情豊かではっきりした発音ができるようになります。
の 脳の発達
よく噛むことで脳の血流量が増えます。子どもの発育を助け、高齢者の場合は認知症予防にも役立つと言われています。
は 歯の病気予防
唾液の分泌が促進されることで虫歯や歯周病を予防できます。歳をとってからも自分の歯で食事ができる期間を延ばすことにもつながります。
が がん予防
唾液に含まれるペルオキシダーゼという酵素が発がん物質の毒性を弱めると言われています。
い 胃腸快調
食品を細かく噛み砕いてから飲み込むことで胃腸への負担を減らすことができます。また噛む刺激が脳に伝わり消化酵素の分泌を促進させるため、効率よく栄養素を消化吸収することができます。
ぜ 全身の体力向上と全力投球
噛み締める力を育てることにより、ぐっと全身に力を入れることができ、体力や運動能力の向上、集中力を養うことにつながります。
よく噛むためにはどんな食事をしたらいいの?
・噛みごたえのある食材を取り入れる
食物繊維が多いもの 根菜類・海藻類・きのこ類・豆類など
弾力があるもの 肉・えび・いか・たこ・こんにゃくなど
乾燥したもの 切干大根・ナッツ類・干し椎茸・煮干しなど
・調理法を工夫する
食材を大きめに切り噛む回数が自然に増えるようにする
食材の繊維の方向に合わせて切り、繊維を残す
りんごやさつまいもなど、皮ごと食べられる果物や野菜は皮付きで食べる
薄めに味付けし、よく噛んで素材の味を味わえるようにする
・食べ方を工夫し、早食いの癖を直す
食べ物を飲み物で流し込まない
一口食べたら箸を置き噛むことに集中する
一口量のを少なくし、ゆっくりよく噛んでから飲み込む
口に入れたものを飲み込んでから次のものを口に入れる
「噛むこと」が健康への第一歩。よく噛む習慣を生活の中に取り入れていきましょう。無理なくできそうなことから始めてみてくださいね!
最後に
このように、よく噛むことは全身の健康につながります。よく噛むためには、よく噛める歯を維持することも大切です。歯医者さんで定期検診を受け、歯の健康を守っていきましょう!
食事は毎日するものであり健康に大きな影響を与えます。食事の内容や摂り方を見直し、改善することで防げる病気もたくさんあります。何かと時間に追われる忙しい現代ですが、日々の食事の時間をしっかりとって大切にしていきたいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました!